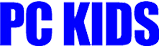人材支援サービスの背景

雇用の流動化と雇用形態
年々雇用が流動化しており、入社1年未満での退職、転職も増加しているようです。近年では、PCやモバイル機器などから簡単に仕事を探すことが可能なため、転職のハードルは下がり続けているのが現状です。「雇用流動化」によって、企業の生産性が高まり、経済成長につながると言われている所以は、企業が知識や経験が高い人材を確保する機会が増えることにつながるためと言われています。
長らく継続されてきた「終身雇用」という人事制度が見直され、欧米式の「ジョブ型人事制度」を導入する企業も増えてきて、ダイバーシティーへの取り組みも積極的に行われるようになってきました。
「終身雇用」とは、新卒から定年までの雇用を約束することで、労働者が安心して働くことができるシステムでした。企業への帰属意識が高く、組織の一員として軸を会社に置いた考え方で働く人が多いことが特徴でした。特に大きな問題が無ければ、終身雇用と年功序列はセットで考えられ、安定して企業に労働力を提供できるシステムでした。
「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」
言うまでもなく、従来の日本における雇用形態の殆どは、「メンバーシップ型雇用」でした。勿論、「メンバーシップ型雇用」は国内においてメインの雇用形態ではあるのですが、外資系企業の台頭と同時に、欧米で主に採用されている「ジョブ型雇用」が急速に増えています。その背景にはどのようなものがあるのでしょうか。
「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」の相違点
「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」には、それぞれどのような特徴があるでしょうか。それぞれの、メリット・デメリットも併せてご紹介致します。
- 「ジョブ型雇用」について
- 近年日本でも増加傾向にある欧米型の雇用形態が「ジョブ型雇用」です。具体的な職務内容を明確に定義し、そのスキルや経験を持つ人材に絞った雇用を行い、その職務にあたる者が退職した場合は、同じくその職務にあたれる知識や能力がある人材を欠員補充のかたちで雇用します。個人のキャリア希望に合致した仕事を探しやすく、専門性を高めやすいという働く側のメリットや、即戦力になる人材が、すぐに職務にあたれるため、教育・育成にかかるコストが抑えられる上に高いレベルの成果を得られるという企業側のメリットもあります。但し、「メンバーシップ型雇用」と違って、どうしても帰属意識は低くなってしまうので、人材が好条件の職場に移動してしまうなど、流動性が高くなってしまうことは否めません。働く側にとっても、年功序列に基づく安定したキャリアパスを望むことが若干難しくなります。
- 「メンバーシップ型雇用」について
- 新卒一括採用を行い、長期雇用・終身雇用を前提として、さまざまな職務を経験しながらキャリア形成を行っていく日本古来の雇用形態です。「ジョブ型雇用」の場合は軸がワーカー本人にあるのに対し、「メンバーシップ型雇用」の場合は軸が会社にあります。安定して長期に働くことができ、年功序列で積み上げていくかたちでキャリアを形成していきます。ワーカーは帰属意識が高く、企業の利益を求める働き方をするため、確実に成果が積み上がりやすいのが特徴です。但し、個人の希望する業務にあたることが難しく、さまざまな業務にあたることが多いため、幅広い経験を積むことができる代わりに専門性は高めにくい傾向があります。転勤や異動もあり、企業内での異動はあっても、同企業内に留まり続けることで人材の流動性が低く、企業側のデメリットとしては、企業内でのイノベーションが起こりにくく、新しい技術が入ってこない傾向が高いことが挙げられます。
| 「ジョブ型雇用」 | 「メンバーシップ型雇用」 | |
|---|---|---|
| 基本概念 | スペシャリスト(特定の分野の専門知識に長けている) | ジェネラリスト(幅広い分野での知識を持つ) |
| 賃金 | 職務内容や実績によって上がっていく | 学歴や年齢、勤続年数によって上がっていく |
| 採用 | 特定の業務を得意とする人、知識や経験がある人に限定して採用 | 業務を限定せず採用。適正を見て振り分ける。 |
| 教育・育成 | 自律的にキャッチアップを設定 | 会社手動で研修・教育を行う |
| 評価方法 | 配置転換や異動 基本的に少ない(本人の希望にもよる) | 異動や配置転換がある可能性は高い |
| キャリアパス | 特定の分野での専門的なスキルの向上を目指す | 幅広い経験を活かして、管理職や経営職を目指す |
| 採用 | 状況により採用、欠員補充 | 新規一括採用 |
「ジョブ型雇用」「メンバーシップ型雇用」それぞれののメリットとデメリット
- 求職者側から見る「ジョブ型雇用」のメリット
-
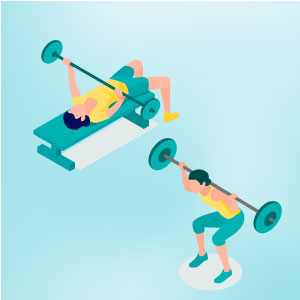
- 成果に基づいて評価されるため、能力や貢献度が認められやすい。
- ジョブ型雇用では、裁量労働制が導入されていることが多く、自分のペース配分で仕事を進めることが可能なため、ワークライフバランスがとりやすい。
- 自分の能力や専門性を活かして仕事ができるため、余計な雑務に時間をとられない。フリーランス、契約社員など自分の生活環境や趣味・ライフワークに応じた多様な働き方を選ぶことができる。
- 自分が得意とする分野に集中して取り組むため、更に知識や経験を深めることができる。更にスキルを積み上げることでより好条件な雇用契約を結ぶことが可能。
- 求職者側から見る「ジョブ型雇用」のデメリット
-

- メンバーシップ型雇用の場合は、企業が研修や教育の場を設定したり、有料の研修費用や書籍購入などを負担するが、ジョブ型雇用の場合は自己研鑽が必要となる。
- 常に成果を意識する必要があるため、精神的な負担がかかりやすい。
- 報酬は職務記述書(ジョブデスクリプション)によってジョブごとに決まっているため、期待以上の成果をあげても、職務記述書に沿った報酬以上の収入を得ることはあまりない。
- メンバーシップ型雇用の場合は、さまざまな職種を経験したり、転勤や異動があるが、ジョブ型雇用の場合には、急な業務変更や廃止により失職するリスクがある。特にエンジニアなどは、プロジェクト単位で採用するケースがあり、プロジェクトが終了すると、職務が不必要になるというパターンがある。
- ずっと単一の職種を掘り下げていることで、他の仕事に就きにくい。
- 企業側から見る「メンバーシップ型型雇用」のメリット
-

- 事業環境の急な変化にも必要なジョブに対応できる人材が得られる。
- 優秀な人材を獲得することで熾烈なグローバル競争に参加できる可能性が作れる。
- 多様な働き方を用意することで良い人材が集まりやすくなる。
- 短時間で高度な成果もしくは成果物が得られるため、経営面での利益が得やすい。
- 事業環境の変化に伴い、短期間で柔軟に事業内容の廃止や追加ができる。
- 成果主義に基づいた人員構成にすることで、常に企業内に競争力が生まれ、高い業績を残しやすい。
- 企業側から見る「メンバーシップ型雇用」のデメリット
-

- 需要が高いグローバルで活躍できる人材や高度な技術を持つIT人材などは、引き抜き等で条件の良い職場に流動しやすい。
- 成果が出せなかった人材も流動しやすいため、他の従業者に負担がかかるなどして、企業の安定性が損なわれるリスクがある。
- ジョブ型雇用の導入には、入・退職する人材の評価を細かく分析する能力がある管理者と、評価制度を綿密に策定する時間と人材が必要になる。
- ジョブごとに異なる賃金体系を設定し、給与システムに反映させる改修費用や、人材の流動がメンバーシップ型雇用に比べ激しいので、人事担当者、経理担当者に負担がかかる。
- 個人の職務内容に基づいたキャリアパスを設計するには、本人の希望やスキル、キャリアを十分考慮する必要する必要があり、設計が難しい。
崩れ行く雇用慣行と今後の課題

以前であれば、多数の人間を一括雇用し、様々な仕事を経験させながら上司や先輩が成長に導くというやり方で企業がが成り立っていました。国内の企業全体がグローバル競争に巻き込まれていく社会変化に伴い、国内独自の雇用慣行も時代の変化に倣うように急激な変化を遂げています。以前から当然のように採用されていた終身雇用制度や年功序列を使い続けることで、グローバル競争に打ち勝つために必要な技術や知識の流入が難しくなり、少子高齢化や働く人の仕事に対する価値観の変化などの様々な要因も加わり、必要に迫られて多様な雇用形態を採用する企業が増えてきました。企業内において、人材派遣、業務委託で働く人の割合が増え様々な価値観を持った人達が交流することで知識や技術のイノベーションが発生すると同時にパフォーマンスの増加も見られるようになります。以前の雇用慣行は次第に欧米型雇用へと変化し、スキルや知識があれば自由に働けるギグワーカーやフリーランサーが年々増加し、副業・兼業という働き方も当たり前になってきました。コロナ禍にリモートワークが普及したことも手伝い、サテライトオフィスやコワーキングスペース、自宅で働くことも昨今では当たり前になっています。高度経済成長期に長らく採用された日本独自の雇用慣行は大きく様変わりし、多様な働き方をする人間で構成された企業内では、働く人達の仕事に対する意識も以前とは大きく変わってきています。
そんな中でも多くの企業では、従来の雇用システムの良いところを残しながら柔軟に労働環境を整え、「成果をあげながらも」つながりを大切にし、働きやすい土壌を構築しています。成果主義のみに偏れば、殺伐とした土壌での労働を余儀なくされる労働者の心身の健康を損ないかねず、企業にとって望ましい成果は得られなくなります。企業内で働く全ての人が不安や焦りを感じることなく、快適に働きながらパフォーマンスをあげられる環境や社内システムを構築することが、多様性の時代の企業存続のための喫緊の課題です。